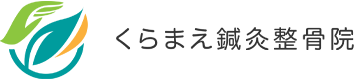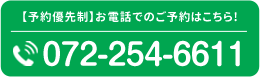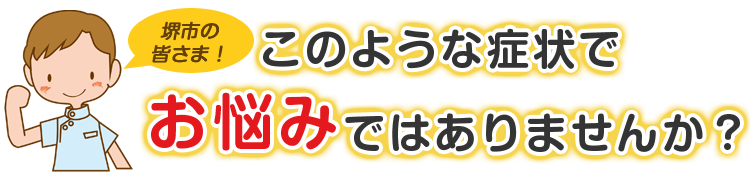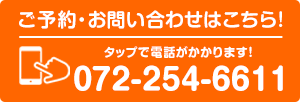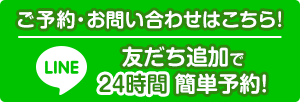足底腱膜炎(足底筋膜炎)
- 踵(かかと)が痛い
- 踵(かかと)の内側、裏側を押さえると痛い
- 朝起きての歩き始めが痛い
- 野球、サッカー、陸上、剣道、マラソンなどのスポーツで踵(かかと)を痛めた
- 足の裏に違和感がある
何で足底腱膜炎(足底筋膜炎)になるの?原因は何?|堺市北区 くらまえ鍼灸整骨院

足裏(足底)の踵(かかと)から足指の付け根までをつなぐ足底腱膜が炎症を起こすことで、痛みを生じます。
踵(かかと)の裏の部分やその内側を押すと痛みを感じることが多い疾患です。

マラソン、ウォーキング、長時間の立ち仕事により足裏の土踏まずに負担がかかることで足底腱膜に傷が入り炎症を起こします。
土踏まずは身体を支えるクッションの役割があります。過度の運動や立ち仕事はそこに負担がかかることで、クッション機能の低下を招きます。

足底腱膜炎(足底筋膜炎)が発生するメカニズム(発生機序)は
過度の負担⇒クッション機能の低下⇒足底腱膜と踵(かかと)の骨の付着部分に炎症⇒足底腱膜の伸縮性低下⇒筋肉の微細断裂⇒組織の変性
となり、腱付着部障害(エンテソパチー)が起こります。
これは、オーバーユース(使いすぎ)による力学的ストレスを何度も腱付着部に受けると、そこに傷が付き、その発生と修復のバランスが崩れることが原因で発症します。
足底腱膜炎(足底筋膜炎)を放置するとどうなるの?|堺市北区 くらまえ鍼灸整骨院

足底腱膜炎(足底筋膜炎)を放置すると、痛みが慢性化し治療期間が長くなってしまいます。
この疾患の多くはオーバーユース(使いすぎ)です。しっかりと休息をとり、適切な治療をしないと余計に長引きます。
痛み始めは放置しても自然と良くなることもありますが、その後、痛みを繰り返していくうちに慢性化してしまいます。

そうなってしまうと治療をしても効果がすぐに出なくなってしまうので、できるかぎり早めに治療するようにしましょう。
ウォーキングやスポーツなどのケースでは、やればやるほど良いという誤解があるように見受けられます。

やり過ぎは逆に筋肉の質を低下させ、筋肉の出力が下がってしまいます。結果としてスポーツに限らず日常生活でのパフォーマンスが下がる可能性があります。
このようなことがケガにつながり、足に関しては最悪の場合、疲労骨折をすることもあります。
少しの違和感や痛みだから大丈夫とは思わずに、早めに治療するようにしましょう。
足底腱膜炎(足底筋膜炎)の予防法は?|堺市北区 くらまえ鍼灸整骨院
足底腱膜炎(足底筋膜炎)になってからの治療も大切ですが、何よりもそうならないようにすることが大切です。
・適度な休息

スポーツなどで足に負担をかけている方は、適度に休息をとるようにしてください。
過度なウォーキングやマラソンは、かえって健康を損ないパフォーマンスが低下します。
立ち仕事などの方で休息をとりにくい方は、足の負担が少ない靴を選ぶようにしてください。
スポーツや仕事で足に負荷がかかっている方は適度な休息をとるようにして、足底腱膜炎(足底筋膜炎)にならないよう予防しましょう。
・定期的なケア

スポーツや立ち仕事などで足を酷使している方は、足底腱膜炎(足底筋膜炎)の治療をできる鍼灸院・整骨院で定期的な施術を受けるようにしてください。
足底腱膜炎(足底筋膜炎)などの強い自覚症状が出る前に、足の状態は少しずつ悪化しています。
症状は突然表れますが、急に足の状態が悪くなっているわけではないことを、肝に銘じるようにしてください。
・温める

温め血行を良くすることは足底腱膜炎(足底筋膜炎)の予防になります。
温める方法としては入浴がおすすめです。温めて血行を良くして疲労物質や痛み物質を溜めないようにしましょう。
お風呂の温度は38℃~41℃くらいに設定し15分~20分を目安に入浴してください。
42℃以上で熱すぎると交感神経が優位な状態になり心拍数や血圧が上がり、リラックスできません。
自宅での入浴の場合は、給湯器やお風呂場の断熱性能の違いにより、すぐにぬるくなることもあります。
入浴は熱すぎず、ぬるすぎず、適当な温度でリラックスして入るようにしてください。
・ストレッチ

ストレッチは血流やリンパの流れが良くなるため、疲労回復やリラックス効果が期待できます。
ストレッチにはいくつか種類があり、今回は代表的なものを3種類ご紹介します。
①スタティックストレッチ(静的ストレッチ)
自分で行い、筋肉を伸ばした状態で30秒程度保ちます。故障のリスクが少なく、一般的なストレッチとして普及しています。
入浴後に行うとより効果的です。

②ダイナミックストレッチ(動的ストレッチ)
自分で行い、反動を用いずに動きをともなったストレッチです。
例として挙げると、肩がこってるときに行う肩甲骨を回す運動はダイナミックストレッチになります。
③バリスティックストレッチ(動的ストレッチ)
自分で行い、反動を用いて行うストレッチです。
小学校の体育などでアキレス腱を伸ばすとき「1、2、3、4」と反動をつけるストレッチがバリスティックストレッチになります。
このストレッチは無理のない範囲で筋肉を伸ばさないと、筋肉を傷つける可能性があります。
体の硬い人や高齢の方は注意して行ってください。
以上が代表的なストレッチです。
疲労回復を目的にするときはスタティックストレッチを中心に行い、準備運動や筋肉をほぐしたいときはダイナミックストレッチを行ってください。
ラジオ体操は、ダイナミックストレッチとバリスティックストレッチを組み合わせたものになるため、最初は少しずつ動かし大きく反動をつけないようにしましょう。
堺市北区くらまえ鍼灸整骨院の足底腱膜炎(足底筋膜炎)の治療法は?
堺市北区くらまえ鍼灸整骨院では、足底腱膜炎(足底筋膜炎)に対して根本から改善できるよう治療していきます。
①徒手療法(MT-MPS)

炎症が強い場合は患部を避けて、筋緊張緩和、循環改善を目的に治療していきます。
足底腱膜炎(足底筋膜炎)に代表される足部の疾患は、下腿部の施術も重要になることがあります。
それは下腿部の循環を良くすることが足部からの脈管系(血液)の経路であるため、そこを施術することで治りが早くなることを期待できます。
②鍼療法(AT-MPS、トリガーポイント鍼療法)

足底腱膜炎(足底筋膜炎)では下腿部に鍼をすることもあります。
スポーツなどで過度に脚を使っている方は、足の痛みと同時に下腿部の筋緊張が亢進しています。
そのような部位には鍼治療も有効です。
鍼治療は手や指では届かない部位に直接アプローチすることができ、その部位の筋緊張緩和、循環改善していきます。
もちろん個人差があるため、鍼は強制ではなく同意の上、施術させていただきます。
③超音波

超音波は主に3つの効果があります。
-
鎮痛効果(疼痛コントロール)
-
筋機能改善効果(筋緊張・ROMの改善)
-
治癒促進効果(硬・軟組織修復)
分かりやすく言うと、筋肉を柔らかくして血行を良くすることで痛みを抑え治癒を促進する効果があるということです。
④エコー観察装置

エコー観察装置では足底の骨棘の確認、疲労骨折などの鑑別をすることができます。
これがあることで今後の治療方針を決めるための有用な手段になります。
⑤テーピング、インソール、ジェルヒールパッド
テーピング、インソール、ジェルヒールパッドを使い足にかかる衝撃を緩和させます。
スポーツなどで休めないときは、テーピングをすることで試合に望む方もいます。

このように堺市北区くらまえ鍼灸整骨院では、足底腱膜炎(足底筋膜炎)の痛みに対して根本から施術していきます。
足底腱膜炎(足底筋膜炎)の痛みのことなら、堺市北区くらまえ鍼灸整骨院にご相談ください。